島民がチャレンジする活動 + 島外応援団の活動
島民は少ないのですが、老いも若きも元気です。
このページでは、島民がチャレンジしている活動や、学者・研究者の皆さんが、口永良部島をフィールドにしての研究や教育活動をされていますが、それらも、今後ご紹介する予定です。
島民による新たな事業展開information
2023年、下記の事業は中断しています。
| 口永良部島活性事業組合 <中断> |
2000年代の後半、危機意識を持った島民は、さまざまの新たな活動を始めました。
その一つが、2007年にスタートした、「口永良部島活性事業組合」で、島の熟年リーダー層と若者が力をあわせたプロジェクトです。
手始めが、屋久島を代表する焼酎「三岳」の原料となるカライモの栽培です。2012年からは、ガジツの栽培も始めました。まだまだ、赤字を抱えており軌道に乗ったとは言い難いですが、島の未来がこの事業にかかっていると云っても過言ではないでしょう。
| 口永良部島未来創造協議会 <中断> |
口永良部島未来創造協議会は、2011年に数名の若手島民により発足しました。離島活性化事業の担い手として、また行政や民間企業や団体などとの協働事業の受け皿として立ち上げられたものです。口永良部島に中短期に滞在する人たちを受け入れることで、雇用を生み出そうとしています。
協議会の設立趣旨によると。
「移住や定住の促進を語る上で、住宅と仕事の問題は、避けて通ることができない最重要課題であるが、その解決は容易ではない。そこで私たちは、自らの力で「口永良部島の未来を創る」ため、長期的な計画やその活動計画など、口永良部島独自のものを区と連携しながら、作らねばならない時期に来ていると確信しました。そこで私たちは、島の文化や歴史に学びつつ、未来を創造することにより、自らの地震と誇りを取り戻し、後世に真に豊かな口永良部島を継承すべく活動を開始しました」
2012年には、 注意<2019年現在、シェアハウスは中止しています>
特定離島ふるさとおこし推進事業の補助金を得て、「口永良部島における移住コンシェルジュ駐在シェアハウスの整備」と題する若者定住推進事業を行いました。事業内容は、移住・交流による地域活性化を支援するために古民家を改造しシェアハウス「和在家」を立ち上げました。シェアハウスは、口永良部島の活性化事業のために働く短期・中期の滞在者の居住拠点にしようとするものです。
シェアハウスの目的や運営の方針を、協議会のFaceBookから転載しました。
| 【シェアハウス「和在家」の運営方針】<中断> (目的) 協議会は、口永良部島の活性と振興をはかる有志と連携し、口永良部 (方針) 上記の目的を達成するため下記を基本的な方針として活動 利用対象者:20代から30代の単身者 条件:地域活動の支援を行うこと 目標:口永良部島のファンづくり |
2013年には、
起業支援型地域雇用創造事業により、シェアハウスの管理運営と島の情報発信を行う管理人を雇用し、プロジェクトを推進しました。
<ご注意>2015年の新岳噴火災害の影響で、現在のところ宿泊できません。
| (社)へきんこの会 |
これとは別に、2006年に島にIターンした若者が始めた事業活動(一般社団法人へきんこの会、2010設立)があります。
「口永良部島ひょうたん島プロジェクト」があり、ホームページでは、「”自然と共に人間らしく生きる”ことを追求し、”若者が農業や漁業に挑戦する環境をつくる”ことにより、雇用を生み出す中で、社会に新しい価値観を伝えたい」と創業された一般社団法人です。
<注>設立者は、現在のところ島外に在住です。
島民による文化活動information
| 口永良部島伝統芸能保存会 |

口永良部島の伝統行事である、棒踊りや「日の本踊り」を継承し、次の代に残そうとする活動です。
代表:久木山 栄一さん

自然の調査・保護の活動
口永良部島は、全島が屋久島国立公園に属しています。
気の毒なほど狭い砂浜ですが、アカウミガメが上陸し、夏には子亀が海に帰ります。絶滅危惧種のエラブオオコウモリが住みついてもいます。
ところが、近年野生のシカが異常に繁殖し、農産物の被害はもとより、山の斜面がシカ道で崩れたり、植生に影響が出ています。
写真:
新岳の西斜面では、マルバツツジが満開でした。
撮影2013年6月27日
<2015年以降の噴火で、現在は壊滅状態です>
| えらぶ年寄り組 <活動中> |
島民のボランティアによる、自然保護の活動に加えて、「えらぶ年寄り組」も自然保護・調査のボランティア活動に加わりました。
「えらぶ年寄り組」は、自然を調査し保護しようと活動しています。しかし、自然を保護するだけではなく、「自然を守る」と「自然を活用する」を車の両輪として、この島での暮らしが立つようにとのねらいです。
「えらぶ年寄り組」は、口永良部島の、生き物や環境、文化や歴史遺産を守り、それらを子々孫々に伝えたいと願い、また、暮らしに忙しい若い人たちを手伝いたいという想いをもつ年寄りボランティアです。
グループの名前は「えらぶ年寄り組」、正式には「子々孫々の口永良部島を夢見るえらぶ年寄り組」です。
活動の紹介です。
| エラブオオコウモリ |

| ウミガメを保護・監視 |

島の北側の漁港では、数頭のアオウミガメが棲みついており、子供たちがさわっても逃げ出しません。
フェリーの入る本村港の近くの向江浜には、年間に数十頭のアカウミガメが上陸します。2012年には、13か所で産卵が確認され子ガメが旅立ちました。
2013年5月から、「えらぶ年寄り組」は、向江浜のウミガメを保護・監視する団体として屋久島町と契約しました。ウミガメの上陸、産卵、子ガメの孵化を毎日のように見守っています。
ウミガメの上陸・産卵状況の調査結果です。
| 植生を守る活動 |
「えらぶ年寄り組」は、シカの食害から 植生を守る活動も行っています。
シカが増えて農作物の被害や、野山の植生に悪影響を与えています。「えらぶ年寄り組」は、シカの頭数調査、植生への影響調査も手掛けています。

その一環として、タカツルランの調査があります。
屋久島環境文化財団に申請していた研究助成が認められました。テーマは「屋久島と口永良部島における照葉樹林内の菌共生に関する保全と研究」で、タカツルランの調査・研究です。屋久島まるごと保全協会、佐賀大学の辻田有紀先生と共に、えらぶ年寄り組も参加しています。
タカツルランの調査、シカの頭数調査などの記録はこちらです。
このページの先頭へ
島をフィールドにした教育や調査・研究活動information
広島大学 魚の生態研究
広島大学の水圏資源生物学研究室は、口永良部島の美浦漁港近くの海をフィールドに、魚の生態を研究している。40数年も続いている息の長い研究で、現在、研究室を率いるのは坂井陽一先生。
 研究室のホームページによれば、「水の透明度が高く、水が温かく、リーフに定住する魚が無数に存在する口永良部島をフィールドにした、サンゴ礁魚類の”社会”、すなわち個体の生き方を詳しく探る研究」と説明されています。
研究室のホームページによれば、「水の透明度が高く、水が温かく、リーフに定住する魚が無数に存在する口永良部島をフィールドにした、サンゴ礁魚類の”社会”、すなわち個体の生き方を詳しく探る研究」と説明されています。
写真は、M Okuboさんの撮影
坂井先生は、2013年5月末に来島され、
そのうちの、いくつかを選んで紹介します。
坂井先生が中心となった研究では、
1)魚の性転換は一方向しかみられないものと考えられていたが、
2)ヨダレカケは陸にあがって子育てまで行うこと。さらに、今、
また、
3)アマミスズメダイの行動圏と餌生物の探索方法
群れ(約80匹)は、
いずれも、毎年5月〜10月にかけて、毎日、
| 授業を一緒に聞かせてもらいました。自然の不思議、子孫をすこしでも多く残そうとする生き物のたくましさ、改めて口永良部島の海の豊かさを知りました。 児童・生徒は、口永良部島の海を誇りに思い、ますます海や魚が好きになったことでしょう。 坂井先生の紹介によると、1970年~2012年までの42年間で、70名の学生・院生が研究のために島に滞在したそうです。そのうち、44名が修士号を、6名が博士号の学位を授与されました。口永良部島から世界に向けて発信された広島大学の研究成果は、世界の海を守り、海からの恵みを利用するための貴重な基礎データです。 この数字を見て、改めてわれわれ島民にとっても、広島大学の学生と研究が、誇らしく思われます。島に溶け込んで暮らしつつ、研究に励む姿を見たり、卒業後の活躍を見聞きすると、彼らがかけがえのない存在であることを実感します。<Y>。 |
2008年には、海より陸の方が好きな魚、ヨダレカケの研究が、NHK総合テレビ「ダーウィンが来た!生きもの新伝説」で紹介されました。
鹿児島大学 多島圏研究センター
鹿児島大学の鹿児島大学多島圏研究センターは,奄美群島や南太平洋の島嶼域における自然や産業,文化に関する学際的な研究をおこなっており、奄美群島での学術調査を毎年実施している。2009年には、口永良部島で調査が行われた。
鹿児島国際大学 エラブオオコウモリの生態を研究
鹿児島国際大学の船越公威先生 や 国崎 敏廣 先生による、エラブオオコウモリの生態研究が、1980年代から続けられています。
舩越研究室ホームページでの、研究紹介を引用します。
Q 舩越公威先生の専門分野・研究概要について教えてください!
A 文系の大学にあって異色の研究を行っており、哺乳類(特にコウモリ類)を対象に野外調査と飼育実験をしています。野外で生態や行動を観察しながらデータを集めるとともに、飼育下では研究手法も学生と一緒に考えながら、個々の現象の評価と実証に努めています。
常識にとらわれることなく、自由な発想で研究する中で、新たな発見もあります。目下研究中のコウモリがこの写真のコテングコウモリです。
アカメガシワトラップ法で捕獲に成功しました。哺育期以外は、雌雄とも単独生活であることもわかりました。
大沢夕志・啓子ご夫妻も

埼玉県の大沢 夕志・啓子ご夫妻も、オオコウモリの研究を続けておられます。2010年には、口永良部島で、講演していただきました。
大沢さん撮影
大沢さんのHPは、「オオコウモリの世界へようこそ」です。
佐賀大学 タカツルラン
佐賀大学の辻田有紀先生は、種子島、屋久島、沖縄などに生育する絶滅危惧種IAのタカツルランを研究されています。タカツルランは、通常の植物のように光合成して栄養を作り出してはいません。立ち枯れるスダジイなどに棲みつく菌根菌が作り出す栄養を取り込んで成長します。自生する北限が口永良部島です。
スダジイがどんなに多くても、環境の悪い森では生育できません。口永良部島には、原始林に近いの照葉樹の森があり、スダジイが自然のままに保全されています。タカツルランは、いかに口永良部島の自然が豊かであるかを教えてくれます。
「えらぶ年寄り組」は「屋久島まるごと保全協会YOCA」の手塚賢至さんらとともに、口永良部島を担当し、採種、見回りなど辻田先生のお手伝いをしています。
タカツルランの研究成果は、辻田先生が日本菌学会の第58回大会でポスター発表されました。名誉なことに「えらぶ年寄り組」も名を連ねています。
北海道大学 ニホンジカを研究
北海道大学大学院文学研究科・文学部の 立澤 史郎 先生は、屋久島や馬毛島、口永良部のシカ、シベリヤのトナカイなどを、保全生態学や野生動物管理学の観点から研究されておられる。 屋久島では、2004年から、ヤクシカ個体群調査および農業被害・生態系被害調査(環境省受託研究)に関わられた。2009年には、「屋久島まるごと保全協会YOCA」のメンバー荒田洋一氏や手塚賢至氏、地元口永良部島の山口正行、貴舩 森、峯苫 健氏らと共に、口永良部島のニホンジカの調査もされている。
屋久島では、2004年から、ヤクシカ個体群調査および農業被害・生態系被害調査(環境省受託研究)に関わられた。2009年には、「屋久島まるごと保全協会YOCA」のメンバー荒田洋一氏や手塚賢至氏、地元口永良部島の山口正行、貴舩 森、峯苫 健氏らと共に、口永良部島のニホンジカの調査もされている。現在、屋久島生物多様性保全協議会や屋久島世界遺産地域化学委員会の委員などを勤められている。また、2010年からは、シベリヤのトナカイに衛星発信機を装着しての研究も始められた。
立澤 史郎先生(人間システム科学専攻 地域システム科学講座)の紹介記事を引用しました。立澤先生の教育・研究の位置づけや取組が良く理解できます。
<文学研究科・文学部の中で野生動物の生態を研究していると聞けば、大半の方が驚くことでしょう。ですが、生物多様性やいわゆる獣害問題は人間社会の問題であり、人文科学の研究者が関わるべき重要課題です。地域社会における野生動物の生態調査や釧路湿原のミンクに代表される外来種対策なども、単なる生物調査ではなく<生物多様性保全という社会問題>として掘り下げるべき研究対象だと認識しています。他大学の文学部では考えにくい我々のような保全生態学者の存在は、実学を重視し、研究の多様性・独立性を尊ぶという北大の伝統の証明とも言えるでしょう。>
鹿児島県立博物館
屋久島・ヤクタネゴヨウ調査隊
東京環境工科専門学校
2013年10月に、東京環境工科専門学校の学生さん10名と先生2名が、自然調査と学生さんの実習のために来島されました。東京環境工科専門学校(TCE)は、長年にわたり屋久島で調査・実習を続けてこられた。今年から、口永良部島も対象にすることにされたようです。
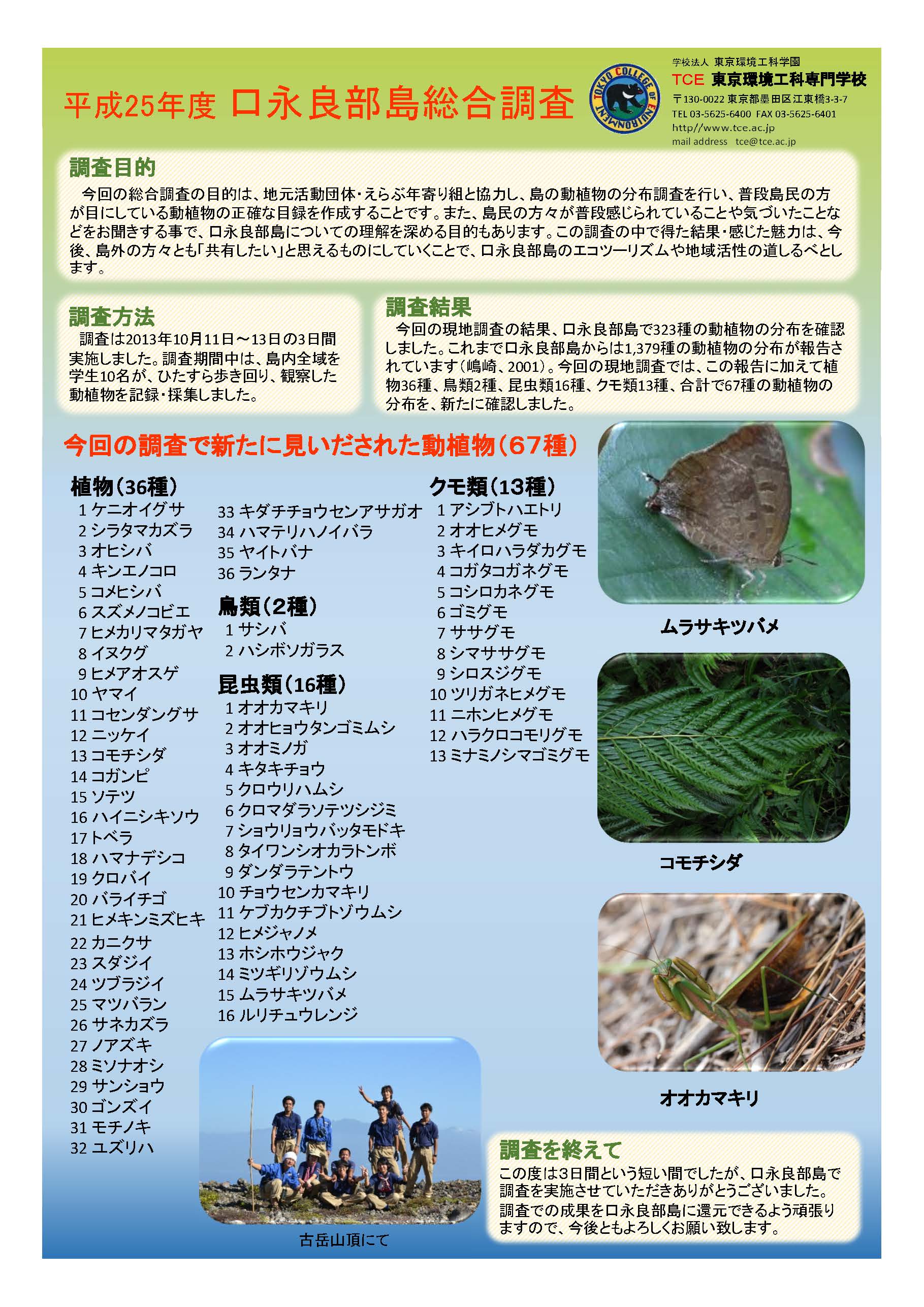
京都大学・防災研究所 火山活動を遠隔監視

口永良部島の活火山、新岳をターゲットにした監視・観測が京都大学によって続けられています。
教員や学生・院生が常駐した観測ではありません。地震計やGPS、テレビカメラ、人工衛星など最先端の観測機器を利用し、インターネットを介してデータを収集しての監視・研究であるところに、現代を感じます。
われわれ島民が目にする機会はありませんが、口永良部島にかかわる数多くの研究が、京大・防災研究所から報告されています。
慶應義塾大学 離島活性化協働プロジェクト

慶應義塾大学の長谷部葉子先生が2011年に始められたプロジェクトです。
長谷部先生は湘南藤沢キャンパス(SFC)の総合政策学部に所属されています。
長谷部葉子研究室のホームページによれば、離島活性化恊働プロジェクトとは「離島である口永良部島の魅力を活かした”教育の機会”と、”新しい交流場所”の提供による離島活性化を目的とした活動」とあります。
「学校がなくなる」ことになれば「島に住めなくなる」・・・・との観点から、教育を切り口として長期的・自立的な過疎離島の活性化を考えようとする試みです。
口永良部島プロジェクト
長谷部 葉子先生の新刊
「今、ここを真剣にいきていますか?―やりたいことを見つけたいあなたへ」講談社(2012年12月)が刊行されました。若者に向けた、想いを込めたメッセージが熱く語られています。
この本では、口永良部島がここかしこに登場します。
。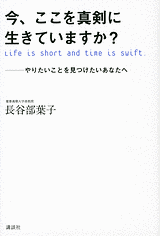
講談社から、2012年12月に刊行されました。
このページの先頭へ
エラブオオコウモリは、絶滅危惧種であり国指定の天然記念物です。
「えらぶ年寄り組」が、2012年10月から、頭数やペリットの調査・観察を始めました。観察の記録です。